2009年12月18日
12月18日/青年・成人期の発達障害者への支援
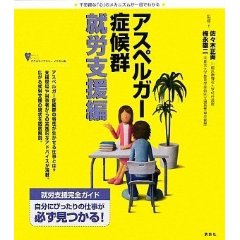 グランシップで午前10時から午後3時まで、宇都宮大学・梅永雄二教授の講演をたっぷりと聴講してきました。
グランシップで午前10時から午後3時まで、宇都宮大学・梅永雄二教授の講演をたっぷりと聴講してきました。テーマは「青年・成人期の発達障害者への支援」。
梅永教授は、3月22日にゆめ・まち・ねっとが主催する講演会の講師、佐々木正美先生との共著「アスペルガー症候群・就労支援編」などを出されている先生なので期待を持って参加しましたが、想定以上に収穫のある講演内容でした。
『成人期に必要なのはソーシャルスキル(その場の雰囲気がわかる、自分の考えを上手に相手に伝えるなど)を身に付けることではなく、ライフスキル(生活全般に渡っての習慣など)を身に付けることである。
』
『大切なのはアセスメント、つまり個人の状態像を理解し、必要な支援を考えたり、将来の行動を予測したり、支援の成果を調べることである。』
佐々木正美先生ばりの痛烈な皮肉もありました。
『特別支援学校では、紙すきをさせたり、さをり織りをさせたりしている。でも、会場のみなさんで紙すきで生計を立てている人は何人いますか?さをり織りをして生計を立てている人は何人いますか?必要なのは、この子はこういう工夫があれば、こういうことができるよと見出してあげることなのです。』
持続力、集中力というのは、仕事によって違うわけです。42.195Kmを完走できたからといって、どんな仕事でも持続力、集中力をもって作業ができるわけではありません。多動な子どもでも関心のあることには集中します。それを見出し、就労に結びつける、それがアセスメントです。
などなど、示唆に富んだ指摘が多々ありました。
とくに、「欠点・短所を指摘するのは誰でもできることです。できることを見つけ出してあげることが専門家の仕事です。」という講話は心に響きました。
特別支援学校・学級に限らず、普通学級の生徒の評価においても、教師たちは、お子さんはこれができません、こんなところが苦手です、ということを親に伝えることのほうが圧倒的に多いのではないでしょうか。
僕らは子どもたちの就労支援をしているわけではありませんが、遊び場の中で、あるいは、たごっこはうすでの関わりの中で、一人ひとりの子どもたちがこんな声掛けをしてあげるとこんな風にできる、こんな環境を提供をしてあげるとこれだけ生き生きとしていられる、こんな関わりをしてあげると信頼関係が築ける、こんな支援をしてあげるとこんなことを得意になってやる、ということをたくさん観察してあげられるスタッフでありたいと心新たにしました。
3月22日 児童精神科医・佐々木正美先生講演会
いわて発達障害サポートセンター「えぇ町つくり隊」さん
児童精神科医・佐々木正美先生
古着リサイクルDAY
12月20日/1%市民活動支援制度を考えるタウンミーティング
12月19日/常識破りの会議上達のコツ&裏技
12月14日/きらり交流会議
児童精神科医・佐々木正美先生
古着リサイクルDAY
12月20日/1%市民活動支援制度を考えるタウンミーティング
12月19日/常識破りの会議上達のコツ&裏技
12月14日/きらり交流会議
Posted by たっちゃん&みっきー@ゆめ・まち・ねっと at 22:35│Comments(0)
│参加してきました







