2010年05月30日
いわて発達障害サポートセンター「えぇ町つくり隊」さん
 藤枝市での児童精神科医・佐々木正美先生の講演に先立ち、岩手県のNPO法人「いわて発達障害サポートセンター えぇ町つくり隊」の活動事例紹介がありました。
藤枝市での児童精神科医・佐々木正美先生の講演に先立ち、岩手県のNPO法人「いわて発達障害サポートセンター えぇ町つくり隊」の活動事例紹介がありました。自閉症児・者が自立して暮らせる町づくりを目指して活動されているそうです。
事例紹介の中でNHKで報道された番組が流されました。
自閉症のある青年たちが買い物に出掛けるのですが、それぞれのお店に青年たちを温かく、にこやかに出迎えるおばちゃんたちがいるのです。
先ずは、まちの中に、自閉症児・者が安心して出かけられる「点」を築いていくという手法。
共感の持てる取り組みでした。
もう一つ、このNPO法人の注目すべきところは、メンバーの多くが教師、保育士などであるということ。
日ごろ、子どもたちと向き合う仕事に携わっている人たちが学校や保育園というハコ物を飛び出して、「まちづくり」という視点から市民活動を展開されていることに驚きを感じました。
2010年05月30日
児童精神科医・佐々木正美先生
ゆめ・まち・ねっとでも度々、招聘している児童精神科医・佐々木正美先生の講演を聴いてきました。
内容はこれまでに何度も聴いている事柄ですが、それでも何度も聴いて、頭の片隅ではなく、頭の真ん中に刻み込みたいと思っています。
今回は「自閉症スペクトラムへの理解と支援~発達障害の共通性と多様性/発達の遅れではなく不均衡なこと~」と題しての講演でした。
・視覚的情報への親和性が大きい。
・関心、興味、課題が狭く強く向かう。
・同時総合機能が困難。
等々の特徴が具体的に示され、まずはそうした特質を持つ人たちのことを理解することが大切であると説かれました。
そしてその上で、
・何々してはいけません、という肯定的な言い方ではなく、これこれをするといいですよ、という肯定的な言い方で伝えてください。
・話し言葉よりも文字や絵カードで伝えるといいですよ。
・あれもこれもではなく、一度にひとつのことがいいですよ。
といった支援の仕方が示されました。
発達障害のことをもっと聴きたいという方、具体的に我が子のことを質問したいという親御さん、担当している児童・生徒へのよりよい支援を求めているという教師、保育士さん、いい機会をご用意しました。
下の記事をご覧ください。
2010年04月17日
古着リサイクルDAY
 今日は「ハートボックス」という市民活動団体さんが富士交流プラザで催していた「古着リサイクルDAY」に参加してきました。
今日は「ハートボックス」という市民活動団体さんが富士交流プラザで催していた「古着リサイクルDAY」に参加してきました。ゆめ・まち・ねっとの活動資金を得るためのフリーマーケット用にみなさんからいただいた古着がすごい量になっていて、なかなか、全部が売り切れないけど、かといって、せっかくのいただきものだからと思っていたら、この催しを見つけたのです。
古着リサイクルDAYは、活用したい人が無料で引き取れるというものなので、活動資金は得られませんでしたが、みなさんのご家庭で不用になった服が再利用されるので、よかったなぁと思っています。
引き取り手がなかった服も「ハートボックス」さんがミャンマの孤児や難民に寄付したり、富士市・富士宮市内の養護施設・授産所に寄付したりという活用をしてくださいます。
詳しくはこちら⇒ハートボックス
今日は冬物を段ボール7箱、ハートボックスさんに託してきました。
夏物は明日!フジスタイルさんが主催されるフリーマーケットに出店します。
売り上げは、参加費無料の冒険遊び場たごっこパークの活動などに活かされます。
みなさん、明日、ふじさんめっせのフリーマーケットにお越しください。
なお、売れ残ったものは、次回、古着リサイクルDAYが7月にあるので、その時にまた、ハートボックスさんに託そうと思います。
2009年12月20日
12月20日/1%市民活動支援制度を考えるタウンミーティング
 富士市市民活動センターで1%市民活動支援制度を考えるタウンミーティングがあり、参加して意見をいろいろと出してきました。
富士市市民活動センターで1%市民活動支援制度を考えるタウンミーティングがあり、参加して意見をいろいろと出してきました。%市民活動支援制度は、千葉県市川市で始まり、現在は千葉県八千代市、北海道恵庭市、岩手県奥州市、愛知県一宮市、大分県大分市で取り組まれている市民活動応援の仕組みです。
自治体によってそれぞれ特徴がありますが、基本は市民税の1%相当額を市民自らが応援したいと選んだNPO法人やボランティア団体の事業計画に賛助するようなイメージです。
(詳しくは上の各自治体名をクリックしてみてください。)
現在、富士市では、市民活動支援補助金という制度があり、ゆめ・まち・ねっとも冒険遊び場たごっこパークと春夏秋冬わんぱくキャンプの活動資金としていただいてきました。
この市民活動支援補助金制度は行政と行政指名の審査員だけで採択の可否や補助額が決められてしまう。それに対して、%市民活動支援制度は市民一人ひとりが選ぶことになるので、税金の使途として透明性が高まり、同時に市民活動が注目されるということで小池智明市会議員が導入を市に提案しています。
また、富士市民協働推進懇話会でも導入の是非が検討されています。
そうしたことをもっと公開の場で議論しようということでの今回の催しでした。
いろんな意見が出されましたが、たっちゃんは次のような意見を出してきました。
①現行の市民活動支援補助金制度はそのまま残し、これまでどおり、各市民活動団体が提案する個別の事業に補助金を出すこととする。
②それに加えて、%市民活動支援制度を導入し、こちらは、市民一人ひとりが直接選ぶ制度であるので、各市民活動団体の個別の事業ではなく、団体そのものを応援する支援金とする。
①に関しては、確かに審査の透明性の確保、あるいは、選ばれたあとの事業実施の透明性の確保が指摘されていますが、審査については、公開にするとか、審査評価を公表するということで担保できると思います。また、実施の透明性も報告書の提出を求め、それを冊子にまとめて公表するなどの方法で担保できると考えます。
ただし、事業実施の透明性については、本来は補助金をいただいている各市民活動団体が率先してやらなければならないことなんですけどね。ゆめ・まち・ねっとでは、ブログや会報、活動発表会、新聞取材依頼などで広く取り組みの様子と成果を発表させてもらっています。
小さな市民活動団体でも、事業計画が優れていれば、専門的な知識を持った審査員にきちんと評価してもらえるという点でも現行の制度は残してほしいなと考えています。
②に関しては、なぜ、個別の事業計画に対する支援ではなく、市民活動団体そのものへの支援にしてほしいかというと、先行自治体の%支援制度を見ると、一日限りのイベントや講座などが多数、名乗りを挙げ、資金を得ています。
ですが、本来、市民活動の強みは、行政が市民からの大きい要望や多い要望に優先的に公共サービスを提供するするのに対して、小さい要望や少ない要望だけど、大切な要望に優先的に手を差し伸べることだと思うのです。
そして、それらの小さい要望や少ない要望は年度当初に事業計画を立てておけるような性質のものばかりではなく、市民活動をやっていく中で偶発的、突発的に寄せられるものなのです。
そんな要望にもすぐに対応できるからこそ、市民活動は行政に比べて柔軟性がある、機動力がある、先駆性があるといった評価をされるわけです。
その柔軟性、機動力、先駆性を生かした対応能力は、まさに市民活動団体が日々、いろんな活動を展開し、研鑽を積み、経験を重ねる中で育まれます。
そのことを具体的に説明するために、12月11日からのこの10日間でどんな活動をしたかを下に記しました。例えば、講演会へ参加しての研鑽や関係機関を訪れての情報交換などは、行政職員だったら、職務で行けますよね。つまりそこには税金が使われているわけです。民間企業でも、出張旅費は出ますし、参加している社員は本来業務に携わっている時間ではないのに、ちゃんと給与は支払われます。
それらは、そのことによって、行政なら職員の力が向上し、よりよい行政サービスができるという期待値として公費が使われるわけですし、企業なら社員の実力が上がり、人脈も広がることで、社の業績アップにつながるだろうという期待値として資金が投入されるわけです。
それに、ゆめ・まち・ねっとの場合には、下に記した10日間の動きの合間、合間で、ブログには書けないような市民活動を重ねています。これは、地道に真摯にコツコツと活動をされているほかの市民活動団体さんも同様なことだと思います。
ですから、%支援制度については、せっかく、市民一人ひとりが選ぶわけですから、日ごろからそれぞれの市民活動団体がどんな活動を展開し、どれだけ市民のお役に立っているか、まちづくりに寄与しているかを見てもらう中で、期待を込めて応援したい市民活動団体を選択してもらい、それが市民活動団体そのものへの支援金となる仕組みにしてほしいと考えるわけです。
実際、 市民のみなさんが、自分の払った税金が無駄な公共事業、行政サービスに使われるよりもせめて市民税の1%くらいは、自分の知っている市民活動団体の支えに活用してほしいと表明し、その団体に提供されることで、市民税の99%は行政が市民のために有効に活用し、1%は市民活動団体が市民のために有効に使う、という広い意味での協働が育まれるのではないかと考えます。
…でも、市民税の1%というのは、実際には600円程度なので、10%=6,000円ぐらいにしてもいいんじゃないかなと思ったりしますけどね。
…ちなみに、記事写真のどこにたっちゃんがいるかわかります?
2009年12月19日
12月19日/常識破りの会議上達のコツ&裏技
 昨年11月、浜松で行われた「NPO協働推進人づくり塾」に事例報告者として招いてくださった会議ファシリテーター普及協会・釘山健一さんが富士交流プラザで講座を開催することになったので、参加をしてきました。
昨年11月、浜松で行われた「NPO協働推進人づくり塾」に事例報告者として招いてくださった会議ファシリテーター普及協会・釘山健一さんが富士交流プラザで講座を開催することになったので、参加をしてきました。添付の新聞記事の写真の一番手前で熱心にメモを取っているのがみっきー。一番、奥にいるのがたっちゃんです。わかりますか?
2時間の講座は、クギケンさんの進行で参加者みんな笑顔、笑顔のうちにあっという間に終了。
ここでは、あえてあまり多くは報告しませんが、例えば、「会議ではお菓子を用意する。それをみんなで食べ合いながら話し合う。場が和んで明るくなるから、どんどん前向きな意見が出る。」というようなことを受講生が次々と学んでいきました。
お菓子を食べながらわいわい、という会議は、ゆめ・まち・ねっとは日ごろもやっていました。
毎年の総会もみんなでおかずやデザート持ち寄りで和やか&賑やかにやっていますからね。
そういうのはやっぱりよかったんだという確認もできましたし、新たに学んだいろんなコツもありました。
コツ&裏技をもっと知りたい方はクギケンさんを招いて講座を開催してもらってくださいね。
NPO法人ゆめ・まち・ねっと
2009年12月18日
12月18日/青年・成人期の発達障害者への支援
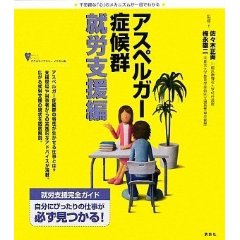 グランシップで午前10時から午後3時まで、宇都宮大学・梅永雄二教授の講演をたっぷりと聴講してきました。
グランシップで午前10時から午後3時まで、宇都宮大学・梅永雄二教授の講演をたっぷりと聴講してきました。テーマは「青年・成人期の発達障害者への支援」。
梅永教授は、3月22日にゆめ・まち・ねっとが主催する講演会の講師、佐々木正美先生との共著「アスペルガー症候群・就労支援編」などを出されている先生なので期待を持って参加しましたが、想定以上に収穫のある講演内容でした。
『成人期に必要なのはソーシャルスキル(その場の雰囲気がわかる、自分の考えを上手に相手に伝えるなど)を身に付けることではなく、ライフスキル(生活全般に渡っての習慣など)を身に付けることである。
』
『大切なのはアセスメント、つまり個人の状態像を理解し、必要な支援を考えたり、将来の行動を予測したり、支援の成果を調べることである。』
佐々木正美先生ばりの痛烈な皮肉もありました。
『特別支援学校では、紙すきをさせたり、さをり織りをさせたりしている。でも、会場のみなさんで紙すきで生計を立てている人は何人いますか?さをり織りをして生計を立てている人は何人いますか?必要なのは、この子はこういう工夫があれば、こういうことができるよと見出してあげることなのです。』
持続力、集中力というのは、仕事によって違うわけです。42.195Kmを完走できたからといって、どんな仕事でも持続力、集中力をもって作業ができるわけではありません。多動な子どもでも関心のあることには集中します。それを見出し、就労に結びつける、それがアセスメントです。
などなど、示唆に富んだ指摘が多々ありました。
とくに、「欠点・短所を指摘するのは誰でもできることです。できることを見つけ出してあげることが専門家の仕事です。」という講話は心に響きました。
特別支援学校・学級に限らず、普通学級の生徒の評価においても、教師たちは、お子さんはこれができません、こんなところが苦手です、ということを親に伝えることのほうが圧倒的に多いのではないでしょうか。
僕らは子どもたちの就労支援をしているわけではありませんが、遊び場の中で、あるいは、たごっこはうすでの関わりの中で、一人ひとりの子どもたちがこんな声掛けをしてあげるとこんな風にできる、こんな環境を提供をしてあげるとこれだけ生き生きとしていられる、こんな関わりをしてあげると信頼関係が築ける、こんな支援をしてあげるとこんなことを得意になってやる、ということをたくさん観察してあげられるスタッフでありたいと心新たにしました。
3月22日 児童精神科医・佐々木正美先生講演会
2009年12月14日
12月14日/きらり交流会議
現在、36団体・10個人が参加していて、ゆめ・まち・ねっとも参加させていただいています。
冒険遊び場たごっこパークをはじめ、ゆめ・まち・ねっとの活動では子どもたちが男女分け隔てなく遊んでいますし、それを支えるスタッフやボランティアのお父さん・お母さんもお互いに認め合いながら、活動をしています。
お母さんたちは、常連になると、「○○さんの奥さん」とか「△△ちゃんのお母さん」という呼び名ではなく、ニックネームで呼び合うようになります。
そんなことで、ゆめ・まち・ねっとも「きらり交流会議」のお仲間にさせていただいています。
その「きらり交流会議」の定例会が12月10日にあり、たっちゃんとみっきーで出席してきました。
先日行われた男女共同参画都市宣言の式典・交流会のふりかえりと次の一歩について、みんなで意見を出し合い、聞き合いました。
また、委員長の再任問題も議論になり、喧々諤々というよりは、よりよいネットワークにしていくためにどうしたらいいのかということがわいわいガヤガヤと話し合われました。
「きらり交流会議」はいつも富士市内のいろんな人と知り合いになれ、いろんな活動を知ることができ、とても有意義な集まりになっています。
たっちゃんとみっきーは、今回の定例会終了後もさらに1時間、参加者と立ち話でいろいろと情報交換をさせていただきました。
こういうつながりもゆめ・まち・ねっとの活動の大きな財産になりますし、活動の中で何か支援が必要になる子どもや親と出会ったときも、頼りになるネットワークになっています。
NPO法人ゆめ・まち・ねっと



